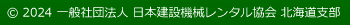皆様には平素より協会運営にご理解とご協力を賜わり心より御礼を申し上げます。
はじめに昨年、元日の夕方に発生しました、石川県能登地方を震源とする能登半島地震で犠牲になられた方々に哀悼の意を表しますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
又、昨年9月下旬には、同じく能登半島で発生しました豪雨災害で、いまだ復旧作業が続いており現在もなお不自由な生活を余儀なくされている皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。1日も早い復旧、復興がなされることを切に願っております。
加えて当協会本部としても、1月の能登半島地震の際には、経済産業省からの要請を受け避難所への災害支援を実施致しました。既に災害協定を締結しております、国土交通省各地方整備局、経済産業省、防衛省、陸海空自衛隊、更には行政機関との連携、協力を推進して災害発生時に国及び地方公共団体が実施する復旧、復興への活動に協力し、業界の社会的責任と、私くしたちが果たすべき役割をしっかりと着実に実行して参りたいと考えております。
さて、すでにご報告の通り、昨年、北海道経済部が行っている「職業能力開発功労者に対する北海道知事感謝状の贈呈」について、当協会北海道支部より、相談役、伊藤豊様(株式会社大鐵 代表取締役社長)を推薦致しましたところ、この度、令和6年10月に受賞が決まり、翌月11月23日に石狩振興局局長より表彰を受けられました。伊藤豊様は皆様ご存じの通り、建設機械整備技能検定及び可搬形発電機整備技術者の教育実習において、技能、技術の有資格者拡大と育成にご尽力され、多くの技能士を輩出しており、講習や実技試験の教育活動を牽引され、現在の基礎を築いてこられました。
当協会としても北海道知事表彰は大変喜ばしい事と考えております。本当におめでとうございます。
次に、政府は物価高への対応などを柱とする、総合経済対策を決定、2024年度補正予算に計上する見込みです。経済対策の柱は3本柱となっております。
- 日本経済・地方経済の成長
(中小企業の経営基盤強化) - 物価高の克服
(価格高騰への対応) - 国民の安心、安全の確保
(国土強靭化、災害復旧)
中でも「防災・減災・国土強靭化の推進」では、激甚化・頻発化する自然災害やインフラの老朽化など危機に打ち勝つ「防災立国」を実現するために「国土強靭化基本計画」に基づき、加えて最近の資材価格の高騰なども踏まえ、必要・十分な予算を確保、地域の防災関係人材とハード、ソフトが一体となった取組を推進するとしています。
又、自然災害への備えに万全を期するためトイレカーや簡易ベッドなど、必要資機材の備蓄を推進し、トイレカーハウスなど登録制度を創設するほか、避難所となる施設の空調整備にも倍増を目指して計画を進めていく見通しです。
更に国土交通省の2024年度補正予算を見ると
- 国民の安心、安全の確保
(成長型経済への移行の礎を築く) - 賃上げの環境の整備
(足元の賃上げに向けて) - エネルギーコスト上昇に強い経済社会
- 防災、減災、国土強靭化推進
中でも防災、減災、国土強靭化では、公共施設等の耐災害性の強化を見据えた公共施設等の耐害性の強化として、道路・鉄道・港湾・空港を始めとした交通インフラのネットワークの整備や局地的な防災、減災対策など、従来からの治山、治水事業も含め多岐にわたっています。
これらを踏まえ国土交通省北海道局は政府の閣議決定後、国土強靭化5カ年加速化計画として、まず防災対策を加速化させると発表しており、災害に強い国土幹線道路のネットワーク機能の確保、治山、治水、河川や港湾での施設耐震化や激甚災害への備えなど広範囲なものとなっております。
加えて昨年末に国土交通省北海道局は2024年度補正予算を前年度ベースより100億円近く上回り、防災、減災、国土強靭化関連にも当てられる見込みです。
又、事業別で見る農林水産基盤整備の補助農業は500億円に達しており、北海道開発事業費総額確保に大きく寄与していると言えます。
こうした中、私くしたちが取組む課題も従前の通り多岐に渡っております。
国土交通省が令和6年4月に発表した「ⅰ-Construction2.0」についても従来の「ⅰ-Construction」とともに高度化するデジタル技術や建設機械の自動化、自律化への取り組みと施工の自動化、遠隔化の技術習得や、安全のための基準要件など、積極的に取組みを進め、国土交通省の方針でもある2040年迄に建設現場を少なくとも3割の省人化、すなわち生産性を1.5倍向上することを目指しており、建設現場のオートメーション化に取り組むとしております。
又、中核となるのがデジタル技術の活用による業務全体の変革を目指す「インフラ分野のデジタルトランスフォーメーション(インフラDX)」を推進して行く方針であり、私達も建設現場の更なる省力化、省人化をともに向上させたいと考えております。
そして近年益々激甚化する大規模地震や風水害、自然災害など、災害協定にもとづく支援体制を図るとともに、発災時への協力体制の整備と具体的な実施策も重要課題です。
また、最近加速しつつある脱炭素化への動きは、さらに大きなものとなる様子です。電動化の促進や義務付けなど法令の改正や規制が予測されます。
又一方では、建機メーカーなど技術革新も加速され、電動化のためには油圧アクチュエーターなど現在のものから大型化が必要であり、省電力・高出力の機器類が開発され、精度が高く多様な動きを可能とすべく、建機が市場へ投入される日も近いと予想されます。更にはバイオ燃料についても注視しなければなりません。B5軽油から現在ではB100燃料を発電機から建設重機類まで使用する軽油代替燃料として利用拡大に向け、実証実験が開始されています。
私くしたち協会としても今後のCO2削減に向け対応をせまられております。
次に価格転嫁ですが、国土交通省では2024年12月施工の改正建設業法で
- 資材価格の転嫁に関する協議ルール
- 現場技術者の専任義務の合理性
- ICTを活用した現場管理の効率化
中でも「受発注者はパートナーの関係にある」と記載し、資機材の価格高騰の際、契約変更の協議ルールについて実効性を確保する様対応を求めております。これらにともない価格交渉を着実に進め、実のある体制を整えたいと考えております。
更に従前通り、足元では「働き方改革」を始めとする、労働環境の改善がせまられており、人材不足や長時間労働の是正、第2、第4土曜日の日の閉所、社員の4週8休、有給休暇の取得など、課題解決には並々ならぬ努力が必要です。
更には外国人受け入れについても現実のものとなって来ております。技能実習制度や特定技能外国人制度もより深く学習する必要がございます。国内での優秀な人材確保も含め将来に向けた人材の育成にも取組みを広げ、有資格者の拡大に努めなければなりません。
本年も「建設機械整備技能士資格」、「可搬形発電機整備技術者資格」、「建設機械レンタル管理士資格と更新時講習」、更には「Webを活用した講習会」などの教育実習の機会促進を図り、技術講習会や資格制度の充実に努めて参る所存でございます。
今後とも協調、協和の精神で連携強化とより良い支部活動を目指し事業を進めて行きます。
どうか会員一丸となって未来に向けた活動にご支援とご協力を頂けます様、お願い申し上げます。
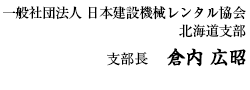
当協会は、昭和45年4月に札幌、室蘭、苫小牧、函館地区業者12社で「札幌建設機械リース業協会」として発足しました。翌年、昭和46年12月に旭川、帯広、北見地区業者の参加を得て全道一本化を図り「北海道建設機械リース業協会」と発展的に改称しました。同年、全国建設機械リース業協会北海道支部として、全国各地区支部(現在21支部)の一員として、中央との結束を深めながら事業活動を行っており、平成24年5月「北海道建設機械レンタル協会」と先駆けて名称変更を行いました。
平成25年4月協会本部が一般社団法人へと移行した後、「全国各地区の任意団体と支部の一体化」が急務となり、平成28年5月第45回定期総会に議案上程、承認後、(一社)日本建設機械レンタル協会 北海道支部として、事業や活動を行って参ります。
| 名 称 | 一般社団法人 日本建設機械レンタル協会 北海道支部 |
|---|---|
| 設 立 | 昭和45年4月 |
| 監督官庁 | 国土交通省 |
| 支部長 | 倉内 広昭 |
| 事務局 | 〒060-0005 北海道札幌市中央区北5条西6丁目1番23 北海道通信ビル 3階 313号室 TEL:011-221-1485 / FAX:011-222-5612 |
| 規約事業 |
|
| 会員数 | 正会員 66社 賛助会員 56社 (令和7年10月31日現在) |
| 具体的な 実施事項 |
|
| 役 職 | 氏 名 | 会社名 |
|---|---|---|
| 支部長 | 倉内 広昭 | エスケーリース(株) |
| 副支部長 | 富山 政紀 | 日本建機サービス販売(株) |
| 〃 | 富田 昌晴 | (株)共成レンテム |
| 常任理事 | 佐々木 康広 | 佐々木鉄工建設(株) |
| 〃 | 藤代 剛士 | 片桐機械(株) |
| 〃 | 小林 潤 | (株)日建機械 |
| 〃 | 志渡 一生 | ニシオレントオール北海道(株) |
| 〃 | 江田 浩 | (株)レンセル |
| 〃 | 渡辺 力 | (株)アクティオ |
| 〃 | 伊藤 浩 | (株)ナガワ |
| 〃 | 野田 敏宏 | 日立建機日本(株) | 〃 | 石田 裕介 | (株)カナモト | 〃 | 恵木 寛治 | 北海産業(株) | 〃 | 中村 健二 | ユナイト(株) |
| 理 事 | 米本 正樹 | (株)稚商 |
| 〃 | 姫野 昌浩 | (株)福地工業 |
| 〃 | 勝浦 隆博 | カツウラ建機(株) |
| 〃 | 蛯名 ユリカ | (株)山川 |
| 監 事 | 山口 正利 | 福地機械工業(株) |
| 〃 | 長嶋 直彦 | (株)長嶋リース産業 |
| 相談役 | 片桐 理 | 片桐機械(株) |
| 〃 | 伊藤 武史 | 北海産業(株) |
| 〃 | 富山 政明 | 日本建機サービス販売(株) |
| 〃 | 伊藤 豊 | (株)大鐵 |
| 参 与 | 岸 良治 | (株)AIRMAN |
| 〃 | 兼本 英喜 | デンヨー(株) |
| 〃 | 定森 岳人 | (株)クボタ建機ジャパン |
| 〃 | 老松 渉 | ユアサ商事(株) |
| 事務局 | 田上 悟 | 事務局長 |